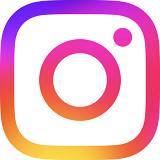はじめに
年末が近づくと、多くの企業でパート従業員から「今年の収入を調整したい」という相談が寄せられます。
これは、扶養控除や社会保険の適用基準となる収入の壁を意識した動きです。
税理士事務所として、企業の人事担当者や経営者の皆様に、パート従業員の年末勤務時間調整について詳しく解説いたします。
パート従業員が意識する「収入の壁」
123万円の壁(所得税の扶養控除)
パート従業員が最も意識するのが「123万円の壁」です。
以前は103万円の壁でしたが、令和7年は123万円までは所得税がかからないこととなりました。
年収が123万円以下の場合、本人に所得税がかからず、さらに配偶者の扶養控除(38万円)を受けることができます。
年収が123万円を超えると、本人に所得税が発生します。
106万円・130万円の壁(社会保険の扶養)
社会保険の扶養からの脱却を避けたい従業員が意識するのが、106万円と130万円の壁です。
106万円の壁は、従業員数51人以上の企業で週20時間以上勤務する場合に適用される基準です。
130万円の壁は、企業規模に関係なく適用される一般的な社会保険の扶養基準となります。
こちらは社会保険の基準ですので、今回の税制改正とは関係なく基準となる収入要件に変更はありません。
2026年10月からは賃金要件(106万円)が撤廃され企業規模と労働時間のみが加入の条件となります。
また、2023年10月から130万円を超えた場合であっても、収入増が一時的なものであった場合、事業主の証明書があれば社会保険の扶養でいられる制度もあります。(しかし、原則連続して2回までを上限とするという制限がついています)
160万円・201万円の壁(配偶者特別控除)
配偶者特別控除に関連する壁として、160万円と201万円があります。
令和7年は160万円以下なら配偶者特別控除を満額(38万円)受けられ、201万円を超えると配偶者特別控除が受けられなくなります。
年末の勤務時間調整の実態
10月から12月にかけての調整要請
多くのパート従業員は、10月頃から年収の計算を始め、収入の壁を超えそうな場合は勤務時間の短縮を申し出ます。
特に11月、12月は「年収を◯万円以内に抑えたい」という具体的な相談が増加します。
今年は大きく税制改正があったため従業員からの問い合わせが多いかもしれません。
企業側への影響と対応策
業務への影響
年末の勤務時間調整は、企業の業務運営に以下のような影響を与えます:
|
影響項目 |
具体的な影響内容 |
|
人手不足 |
年末繁忙期に必要な労働力の確保が困難 |
|
業務の停滞 |
経験豊富なパート従業員の休暇により業務効率が低下 |
|
他の従業員への負担増 |
正社員や調整しないパート従業員の労働負荷が増加 |
|
顧客サービスの質低下 |
サービス業では顧客対応の質に影響する可能性 |
企業の対応策
-
事前の人員計画
年末の勤務調整を見込んだ人員計画を立てることが重要です。
10月中に各従業員の年収見込みを把握し、調整希望者を早期に特定します。
-
代替要員の確保
– 短期アルバイトの雇用:年末限定の短期雇用を積極的に活用
– 派遣スタッフの活用:繁忙期に限定した派遣スタッフの導入
– 正社員の活用:正社員の残業や部署間異動による対応
-
業務の効率化
– 業務プロセスの見直し:年末に向けて業務を効率化
– IT化の推進:システム導入による省人化
– 業務の前倒し:年末業務の一部を前倒しで実施
法的な注意点と労務管理
労働契約上の注意事項
勤務時間調整に応じる際は、以下の法的事項に注意が必要です
- 労働契約の変更
勤務時間や日数の変更は労働条件の変更にあたるため、書面による合意が望ましいです。口約束だけでは後々トラブルの原因となる可能性があります。
- 最低勤務時間の確保
雇用保険の加入要件(週20時間以上)を下回る場合は、雇用保険の資格喪失手続きが必要になります。
- 有給休暇の取り扱い
勤務日数が減少した場合、有給休暇の付与日数も比例して変更される可能性があります。
社会保険・雇用保険の手続き
勤務時間調整により社会保険の加入要件を満たさなくなった場合は、速やかに資格喪失届を提出する必要があります。
また、翌年の加入要件を満たす見込みがある場合は、事前に再加入の準備を進めておくことが重要です。
まとめ
パート従業員の年末勤務時間調整は、税制や社会保険制度の複雑さから生じる現象です。企業としては、従業員の働き方への配慮と業務運営の両立が求められます。
重要なのは、早期からの計画的な対応です。
従業員との十分なコミュニケーションを図りながら、柔軟な働き方を提案し、必要に応じて代替要員の確保や業務効率化を進めることが成功の鍵となります。
また、制度改正の動向を常に把握し、従業員に正確な情報提供を行うことで、不要な勤務調整を避けることも可能です。
税理士等の専門家と連携しながら、従業員と企業の双方にとって最適な解決策を見つけていくことをお勧めいたします。