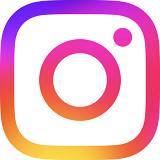1.はじめに
令和7年3月31日に令和7年度税制改正法案が参院本会議で可決され、成立しました。
今年は衆議院で与党勢力の議席が過半数割れしているため、昨年末に発表された税制改正大綱から一部が修正されています。
そこで今回はその改正法案のうち新たに創設された、基礎控除の特例についてお話したいと思います。
2.基礎控除とは
基礎控除とは、所得税の計算において、すべての納税者が所得金額から差し引くことができる控除です。以下の表の通り、令和6年(2024年)までは、合計所得金額が2,400万円以下の場合、一律48万円が控除されていました。
3.令和7年基礎控除の特例の概要
令和7年の税制改正では、この基礎控除額が見直され、所得金額に応じて控除額が変動する特例が導入されます。
具体的には、以下のようになります。
【令和6年(2024年)まで】
|
納税者の合計所得金額 |
基礎控除額 |
|
2400万円以下 |
48万円 |
|
2400万円超2450万円以下 |
32万円 |
|
2450万円超2500万円以下 |
16万円 |
|
2500万円超 |
0円 |
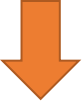
【令和7年(2025年)、令和8年(2026年)】
|
納税者の合計所得金額 |
基礎控除額 |
|
132万円以下 |
95万円 |
|
132万円超336万円以下 |
88万円 |
|
336万円超489万円以下 |
68万円 |
|
489万円超655万円以下 |
63万円 |
|
655万円超2350万円以下 |
58万円 |
|
2350万円超2400万円以下 |
48万円 |
|
2400万円超2450万円以下 |
32万円 |
|
2450万円超2500万円以下 |
16万円 |
|
2500万円超 |
0円 |
この特例により、特に所得の低い層においては、基礎控除額が増加し、税負担が軽減されることになります。
この「基礎控除の特例」は令和7年12月1日に施行され、令和7年分の所得税に適用となります。
会社員は令和7年12月の年末調整で適用されます。
個人事業者等は令和7年分の確定申告で「基礎控除の特例」を適用します。
4. 特例導入の背景
この特例が導入された背景には、近年の物価上昇や社会経済情勢の変化があります。
政府は、これらの影響を受ける低所得者層の生活を支援するため、基礎控除額を引き上げることを決定しました。
5. 特例の適用期間
この基礎控除の特例は、令和7年分および令和8年分の所得税について適用されます。
令和9年分以降は表の青字の部分については一律控除額58万円に減額される予定です。
今後の税制改正の動向に注意が必要です。
6. 納税者への影響
この特例により、多くの納税者の税負担が軽減されることが期待されます。
特に、合計所得金額が336万円以下の層においては、基礎控除額が大幅に増加するため、税負担軽減の効果が大きくなります。
7. 注意点
・合計所得金額が2,350万円を超える場合は、控除額は令和6年以前と変更はありません。
基礎控除額が段階的に減少し、2,500万円を超えると控除額はゼロになります。
・この特例は、所得税のみに適用され、住民税には適用されません。
・また、給与所得控除も改正され、最低保障額が55万円から10万円引き上げられ65万円になります。
(給与等収入が190万円以下まで)
・基礎控除と給与所得控除の改正を合わせると、所得税の非課税枠は現行の年収103万円から年収
160万円(基礎控除額95万円+給与所得控除額65万円)に変わります。
・改正制度の適用が令和7年12月1日となっているため、毎月の給与等による源泉徴収事務は上記の
基礎控除の特例は反映されていない現行制度に基づく税額表等によりおこないます。
8. 納税者が準備すべきこと
納税者は、この特例の内容を理解し、自身の所得金額に応じた基礎控除額を確認する必要があります。
また、ご自身で確定申告される際には、この特例を適切に適用し、税額を計算することが重要です。
9.まとめ
令和7年の基礎控除の特例は、低所得者層の税負担軽減を目的とした重要な改正です。
改正税制は令和7年12月1日のため、11月30日以前に死亡により退職したり、外国へ出国される場合はこの適用はなく、一旦改正前の現行制度により所得税の精算が行われます。
この改正制度を適用するには確定申告をする必要がありますのでご注意下さい。